出題基準:
- 未熟児・低出生体重児・多胎児
- 医療的ケアの必要性の高い児(先天性疾患、心身障害、慢性疾患)
- 社会生活において困難を抱える児(発達障害)
- ひとり親、血縁関係のない親子
- 特定妊婦、在留外国人、在外日本人、帰国日本人
- 貧困、ドメスティック・バイオレンス(DV)
【 文 献 】
- 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
- 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
- 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
- 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022
- 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022
*今回は文献(1)(2)を参照しながら、ノート作成しています*

支援ニーズの高い対象と家族の健康課題と支援
未熟児・低出生体重児に対する支援
低出生体重児が生まれた場合は、保護者は速やかに市町村に届け出なければならない(母子保健法 18条)
未熟児、低出生体重児に対しては、養育上必要な場合に市町村の保健師等が訪問指導を行う(母子保健法 19条)
未熟児、低出生体重児の母親は、児の子育てや発育・発達に対して不安が強くなることも予測される。保健師の訪問指導では児の成長を適切にアセスメントするとともに、母親の訴えに耳を傾け(傾聴)不安軽減に努めることが重要。
成長発達障害のリスクがある児に対する支援
障害のある子どもを家族がどのように受けとめているかを把握し、必要な支援は家族を主体として行う。
高度な医療処置(人工呼吸器や胃瘻の管理等)が必要な場合は、入院中から自宅の療養環境について情報収集を行い、アセスメントしたうえで退院カンファレンスに参加し、多職種と連携しながら支援を行う。
親の会(同じ障害を持つ子どもを育てる)への参加は、悩みを共有でき不安解消の機会として有効である。
放課後等デイサービスとは、就学している障害児が授業終了後または学校休業日に通う場所である。
医療的ケア支援法:医療的ケア児及び家族に対する支援に関する法律
- 医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止することで、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄与することが目的。
- 法律の施行に伴い、自治体は保育所や学校等で医療的ケア児を受け入れていくための支援体制を拡充していく必要性がある。
- 保護者の付き添いなしで医療的ケア児が施設に通えるよう、保健師や看護師を配置すること、また医療的ケア児支援センターを都道府県が設置することが求められている。
ドメスティック・バイオレンス(DV)
一般的に配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力を指す。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」においては、被害者の多くは女性である。
健康上のリスクをもつ母子への保健指導
1 育児力の弱い家族への支援
- 未婚の母子家庭や乳児死亡の経験をもつ家庭、若年夫婦、多問題家族、母親に病気または障害がある時などは、育児力が弱い傾向にある。
- 望まない妊娠の場合、妊娠届を出さず出産することもありハイリスク出産となる。
- 母親の精神障害や知的障害等には、育児支援が必要である。
- 家族やパートナーに協力を得るための手助けをするのも保健師の仕事である。
- 医師、ケースワーカー、民生委員などと連携し支援することも重要である。
2 障害児への支援
- 保健師は家庭訪問などを通して、母親や家族の気持ちを十分受けとめ、前向きな子育てができるよう支援する。
- 家庭での療育体制が整い、親が子の障害を受け入れて積極的になった段階で、地域の親の会などの情報を提供する。
- 成長に合わせて施設への入所・通園についての情報を提供する(育成医療については障害者自立支援法〈現在の障害者総合支援法〉に移行し、自立支援医療費の支給に変更されている)
3 在留外国人母子に対する支援
- 2021(令和3)年6月末現在、282万人強の外国人が日本で生活している。
- 母親が外国人の場合、妊娠・出産・育児について言語、文化、習慣等の違いを感じ、不安に思うことが多い。
- 日本では全ての外国人母子に、医療法、予防接種法、母子保健法、児童福祉法に基づく支援が行われるようになっている。
- 外国語版の母子健康手帳の活用や通訳ボランティアの協力を得ながら支援を行う。
4 孤立化した母子への支援
- 核家族化が進み隣人との交流も希薄化している。
- 専業主婦は、心身の疲労と閉塞感から就労している女性以上に育児不安が生じやすいといわれている。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより行動制限が行われ、保育施設や子育て支援施設等の利用制限がなされ、更なる孤立化が問題となっている。
- 保健師には民生委員・児童委員・母子保健推進員と協働し、支援していくことが求められている。
【hokenCから一言】
「久々にタブレットを使用しながら絵でも描いてみようかな〜」と考え、やりかけてみたのですが、操作が上手くいかず断念しました。せっかくの時間を有効に使おうということで、本日2回目のノート作成をしました。
PCを打っていると、市町村保健師をしていた頃のことを思い出しました。国試対策のノートにしてしまうと数行の内容に簡略化されてしまいますが、地域にはいろんな親子の物語があるのだと感じています。
私の場合、絵を描くのなら紙ベースのものの方が良いのかもしれませんが、少しずつデジタルの世界についても勉強してみようという感じで頑張っています。
しかし、いつの時代も人間や動物の子育てや看護、介護については、手作りであり続けて手間暇がかかるようになっていますね。hokenCとしては、アナログの世界とデジタルの世界を行ったり来たりしながらバランスをとって過ごしていきたいな〜と思っています。
次回で母子保健の領域は一旦終了して、次に進んでいきたいと考えています。
母子の次は成人保健を予定しています。
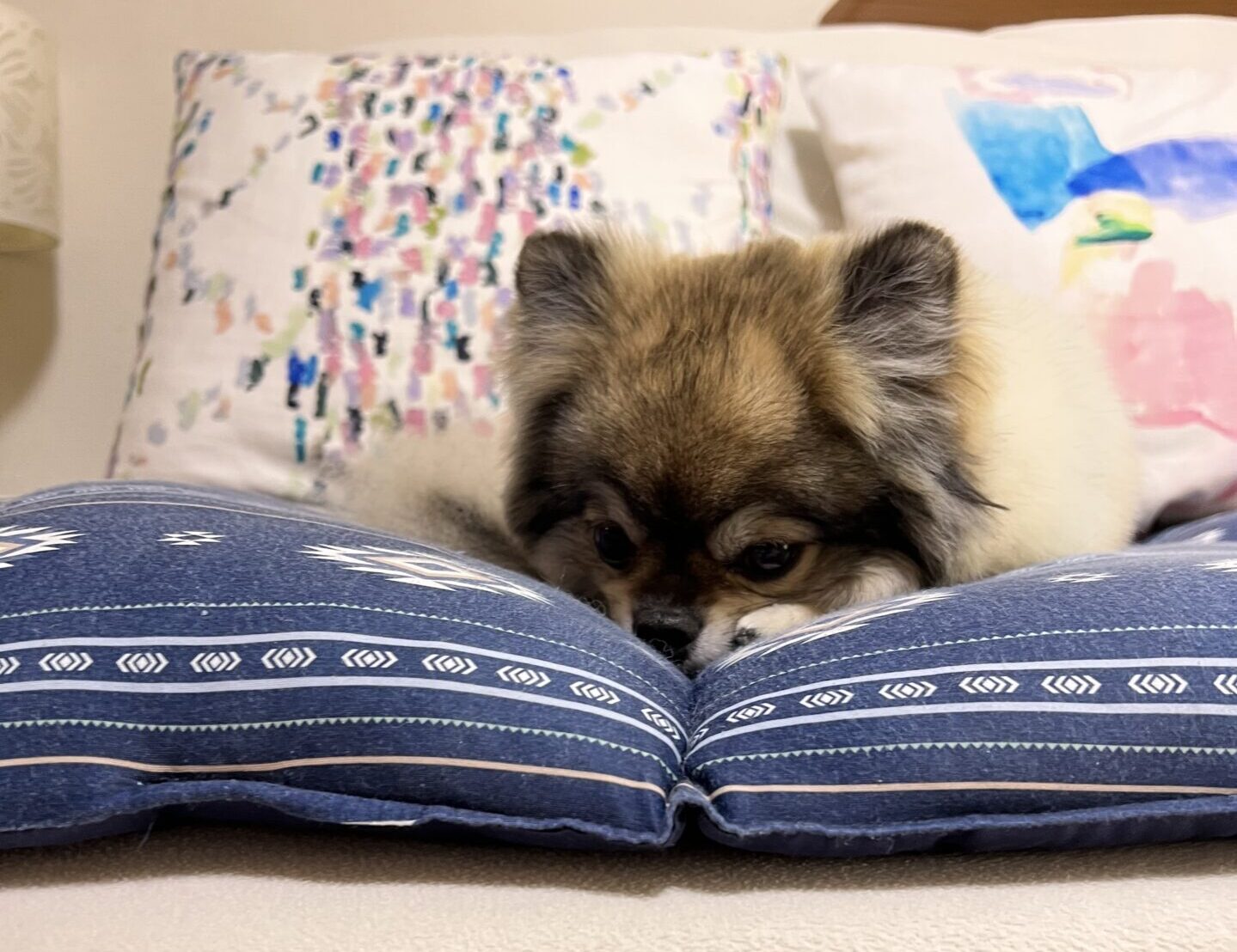
コメント