hokenCから
今回から「保健だより」というかたちで、心身の健康についてまとめていきたいと思っています。参考文献は「国民衛生の動向」がメインで、いろんな書籍を参照しながら情報収集し、学習できれば良いなと考えています。
保健師の国家試験対策については先日、1クール目を終了させ今は、2クール目ということになります。今後は難しい内容をいかにまとめれば有用な健康情報になるのかを追求していきたいと思っています。
ちょっと大袈裟ですがむしろ、学校で手渡されるような「保健だより」のような気軽に読めるような内容にするのが真の目標です。どのように生活すれば楽しく健康的な毎日が送れるのかを、私なりに考えて過ごしていきたいと思っています。
生活者としては、いろんな困難にも遭遇し悩みが絶えないような状況とも考えられますが、少しずつ前進するための学習と考えて、この「ごまごまプレイス」で発信を続けていきたいと思っています。
今後ともよろしくお願いします。
生活習慣病とは
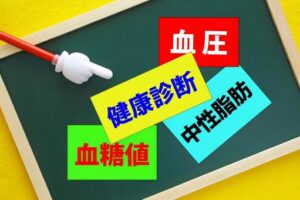
生活習慣病の危険因子
危険因子には大きく分けて3つあると考えられています。
この中で、どの項目が改善可能なのかを考えて、生活習慣病を予防・回避できたら良いのに・・と思っています。
- 遺伝因子
歳をとったり(加齢)、性別、家族歴、人種 - 環境因子
病原体、有害物質、ストレッサー、気候 - 生活習慣
食習慣:2型糖尿病、肥満、脂質異常症、高尿酸血症、循環器疾患、悪性腫瘍、歯周疾患(家族性・先天性のものは除く)
運動習慣:2型糖尿病、肥満、脂質異常症
喫煙:悪性腫瘍、循環器疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、歯周疾患
飲酒:アルコール性肝障害、悪性腫瘍
日本の生活習慣病の概念
昭和の時代は、生活習慣病によく似た病気のことを「成人病」といっていましたね。
私が保健師学生の頃はまだ、成人病対策のための健康教育や健康相談という形で事業が展開されていました。
成人病とはいったいどんな病気のことをさしていたのでしょうか?
昭和32年に開催された成人病予防対策協議連絡会の議事録では、「成人病とは主に脳卒中や悪性腫瘍(がん)、心臓病などの40歳前後から急に死亡率が高くなり、しかも全死因の中でも高位を占め、40〜60歳くらいの働き盛りに多い疾患と考えられる」と書かれていたそうです。
成人病は本来、加齢ととに有病者が増加するものなので、今の日本のような高齢化が進んだ国では当然、患者数・死亡者数共に多くなるというのは当然です。
成人病については、さまざまな調査や研究がなされたと思います。その結果、有病者の増加は高齢化だけが関連しているのではなく、喫煙や食生活、運動などの生活習慣が疾患と関連しているということがわかってきました。
平成8年の公衆衛生審議会意見具申では「生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性について」において「食習慣、運動習慣、休養、飲酒等の生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群」として生活習慣病の概念が誕生しました。
以前の成人病対策においては、健診などで疾病を早期発見・早期治療するという二次予防が重要視されていましたが、生活習慣病においては生活習慣の改善を目指し発症を予防するという一次予防の方針を新たに導入することになりました。
平成12年度からは具体的な施策として「21世紀における健康づくり運動(健康日本21)」がスタートして、24年度まで継続し、25年度以降は新たに「健康日本21(第二次)」が現在進行形で実施されています。

生活習慣病の現状:死因の5割が生活習慣病
(がん・心疾患・脳血管疾患)
-
糖尿病
糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型は生活習慣とは関係なく小児期に発症する疾患で、2型は運動や食事といった生活習慣が関連しています。
日本では糖尿病の可能性が否定できない者(ヘモグロビンA1cが6.0%〜6.5%未満)と糖尿病が強く疑われ者(ヘモグロビンA1cが6.5%以上)を合計すると約2,000万人と考えられています。とても多いですね。
しかし糖尿病で亡くなる人は、全死亡の1.0%というデータがあります。つまり糖尿病は、主要な死因である脳血管疾患や虚血性心疾患の危険因子であるという点が重要です。糖尿病は早期では症状がわかりにくい病気ですし、むしろ合併症が進行してしまうことが怖いという疾患です。中でも糖尿病性腎症は患者数が多く、令和2年に新規で透析を導入した患者数の約4割(40.7%)がこの糖尿病性腎症だったということです。人数にすると15,690人が新たに糖尿病で透析を開始したということです。 -
高血圧症
高血圧症は脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性心不全などの疾患の危険因子です。
この疾患で受診する人は40歳代後半から急激に増加しますが、どうも若年期からの生活習慣が影響しているようです。
高血圧症も自覚症状がほとんどなく、血圧計で測定をしてはじめて高いということがわかる疾患です。
日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、高値血圧が「収縮期血圧130〜139mmHg かつ/または、拡張期血圧80〜89mmHg」となっています。つまりこれ以上の血圧の人は気をつけ経過をみていかなくてはならないということになります。 -
脂質異常症
脂質異常症も高血圧症と同様に自覚症状がなく、40歳代後半から急激に増加します。日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」では従来、高脂血症といっていたものを脂質異常症と疾患名をあらためています。
以前は総コレステロール値を予防や診断の基準にしていましたが、平成29年に改定されたガイドラインではLDLコレステロール値とHDLコレステロール値をそれぞれ別々に設定しました。
脂質異常症は虚血性心疾患の危険因子で、特にLDLコレステロールの高値(140mg/dl以上)は、各項目の中でも最重要視されている項目です。
その他の項目ではトリグリセライド(中性脂肪)150mg/dl以上、non-HDLコレステロール170mg/dl以上は留意が必要な所見とされています。 -
肥満とやせ
BMI = 体重kg ÷ (身長m)2が広く使われており、25以上が肥満で18.5未満がやせと判定されています。
令和元年の国民健康・栄養調査では肥満の割合が男33.0%、女22.3%という結果でした。 -
脳血管疾患(脳卒中)
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞に分けられます。令和3年の死因順位は第4位で10万4,588人の方がお亡くなりになっています。
脳卒中対策では危険因子の回避を目指した一次予防対策や発症後の医療とリハビリテーションが重要とされています。 -
心疾患(心臓病)
令和3年の死因順位が第2位で21万4,623人の方がお亡くなりになっています。
虚血性心疾患については、発症後医療機関に到着するまでの対応が予後を大きく左右します。このコロナ禍で救急搬送がスムーズに行えない状況もあると考えると、感染症対策以外の医療の重要性や確保の困難性を感じますね。
【 文 献 】
一般財団法人 構成労働統計協会「国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第69巻9号 通巻第1081号」、2022、P82-85
荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022、P89・262
医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022、P193
次回の保健だよりは「生活習慣病の対策」から
- 特定健康診査・特定保健指導
- 健康増進事業
- 循環器病対策

コメント