hokenCから
今回は新型コロナウイルス感染症(COVID -19)の発生から現在に至る状況について振り返ってみたいと思います。
COVID -19は2019年12月の発生から世界中に蔓延し、現在でも必ず毎日感染者数の報告が各所でなされています。
私自身もステイホーム中は、何をすべきか模索しながら生活していたように思います。
仕方なく家の断捨離を決行し多くの書籍(専門書)も処分しました。
このコロナ禍で現場の保健医療福祉の従事者のみなさんが悪戦苦闘されていることもニュース等で知りました。改めて「保健師の仕事」にやりがいを感じる今日この頃です。
*「保健室だより」としては、医学的な情報が圧倒的に不足しています。
新型コロナウイルス感染症については、さまざまなサイトでまとめられたものが多くありますので、詳細については是非そちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の経緯を振り返る
新型コロナウイルス感染症の国内状況
令和元(2019)年
12月:中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎が発生
令和2(2020)年
1月:肺炎の原因が新型コロナウイルスによるものと判明し、感染症法に基づく指定感 染症(2類相当)、検疫法に基づく検疫感染症に指定されました。またWHOは公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)であると宣言しました。
2月:大型客船「ダイアモンド・プリンセス」で感染者を確認
全国小中学校の一斉休校の要請がなされ、この時期にWHOはCOVID-19と命名しました。
3月:WHOが新型コロナウイルス感染症のパンデミックとみなし、世界的な感染が広がっていきました。
4月:緊急事態宣言を発令(当初7都道府県、その後全都道府県に発令。5月全面解除)
6月:新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の提供開始
7月:新型コロナウイルス感染症対策分科会を設置
11月:予防接種法改正(新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種の特例が認められるようになりました)
12月:Go Toトラベル事業の全国一時停止
令和3(2021)年
1月:緊急事態宣言を発令(当初4都県、7府県追加、3月全面解除)
2月:新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正(まん延防止等重点措置の創設、入院を拒否した感染者への罰則等)
感染症法の改正(新型インフルエンザ等感染症に新型・再興型コロナウイルス感染症を追加)
医療従事者から先行してワクチン接種開始が開始
4月:まん延防止等重点措置を3県に適用、緊急事態宣言を発令(当初4都府県、6道県追加。6月に沖縄を除き解除)
7月:緊急事態宣言を発令(当初は東京と沖縄、のちに19道府県追加。9月全面解除)
東京オリンピック・パラリンピックを無観客で開催
11月:ワクチン検査・パッケージの導入
オミクロン株等への対応のため外国人の新規入国を原則一時停止
令和4(2022)年
1月:感染急拡大によるまん延防止等重点措置の適用拡大(3月に全面解除)
6月:新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議提言
新興感染症等を踏まえた医療提供体制
令和3年の医療法改正によって、新興感染症等の感染拡大時における医療の確保に関する事項が追加され、令和6年4月から施行されることになっています。
日本では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、有効なワクチンや治療薬について特例承認や優先的な審査によって、早期に薬事承認できるよう取り組まれていました。今後はさらなる早期化に向けて「ワクチン開発・生産体制強化戦略」や「経済財政運営と改革の基本方針2021」「成長戦略フォローアップ」で緊急時の薬事承認について結論を出しました。
令和4年3月には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の改正案が国会に提出され、成立しています。

保健所による積極的疫学調査とは
保健所では「感染源の推定(さかのぼり調査)」「感染者の濃厚接触者の把握」「濃厚接触者の適切な管理(行動制限)」といった従来の感染症対策で実施されていた積極的疫学調査(接触者調査)に取り組んでいました。この調査ではクラスターの発端が明確になるよう濃厚接触者のリストを作成し、感染拡大防止に努めています。
しかしこの感染症は、無症状や軽症の感染者も多く、潜在的にクラスターが発生してしまうという特徴もあります。
特に高齢者や基礎疾患を有する人は、重症化するリスクも大きく保健所職員の皆さんは多忙な勤務をこなしながら現在に至っています。
ワクチンの予防接種
令和3年2月14日にファイザー社製のワクチンが薬事承認され、同月17日から接種が開始されました。5月21日には、武田/モデルナ社とアストラゼネカ社のワクチンも薬事承認され、今では4回目の接種が行われるようになっています。
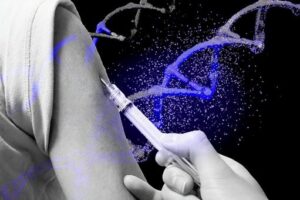
学校生活はどうなった?
新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年2月に文部科学省から小学校等の一斉臨時休業が要請されました。自宅での学習が可能になるよう各自治体で創意工夫し、リモートで授業ができるようタブレットの配布などが行われました。
学校再開後もマスクを常時着用し、給食時の会話を控えたり、大きな声を出すような活動が控えられたり・・・といろいろな制限がありました。
近距離で対面方式となるグループワークや合唱・合奏、調理実習なども行えないという期間がありました。未知なるウイルスに対する策としては仕方ないことだったと考えられますが、子どもたちの発達や成長を促す環境という点においては、マイナス部分があったことは認めざるを得ない状況です。
2020年には文部科学省が「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜学校の新しい生活様式〜」を作成し、地域の特性に応じた対策が行われています。
*最新情報については厚生労働省のサイトでご確認ください*

【 文 献 】
一般財団法人 構成労働統計協会「国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第69巻9号 通巻第1081号」、2022、P 19-20
荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022、P385-386、P465
医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022、P294-295

コメント