 hokenCから
hokenCから
今回は「産業保健」について過去問チャレンジしました。この領域は前回の国試でも比較的多く出題されていたところではないかと思います。
産業保健は法律・規則・ガイドラインの改訂など社会的な変化に対応した問題が作成される傾向にあります。問題集の解説を必ず読んでおくことが大切ですが、今回は「国民衛生の動向」第8編の労働衛生の箇所が特に重要と感じました。
過去問を解いた直後に読んでみました。すると細かいけれど過去に出題されていた項目を散見することができました。
今回はアウトラインと思える部分を一部ノートにまとめています。
受験生の皆さんは手持ちの「国民衛生の動向」にざ〜っと目を通していただけると良いかなと思います。
残暑が根強く感じられる初秋ですが、秋を楽しみつつ、台風の接近等に備えた計画を立てていただけると良いかと思います。
hokenCは最近PC入力をしている日が多くなって、gomaちゃんとあまり遊べていません。
もう少し涼しくなったら公園に出かけたいなと考えています。

「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」P348-368
産業保健の過去問題・予想問題・状況設定問題は以下の内容について解きました。
衛生管理者、石綿による疾病に関する労災保険給付、健康障害の再発防止策、労働安全衛生法、産業保健総合支援センター、騒音の低減、作業管理、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン、安全衛生管理体制、労働安全衛生マネジメントシステム、産業保健の制度としくみ、業務上疾病、健康管理手帳の交付対象となる物質、労働者の心の健康増進、過重労働による健康障害の防止、労働者のハラスメント防止措置を規定する法律、女性労働者への健康支援、障害者雇用、休職者支援、一般健康診断、特定業務従事者の健康診断、製造工場における腰痛の予防、特定保健指導の面接、特殊健康診断の有所見率
(以下、状況設定問題)
腰痛対策、企業におけるメンタルヘルスケア、高年齢労働者の労働災害防止対策、ストレスチェック

「国民衛生の動向 2022/2023」P 319-331 を復習
労働衛生行政のあゆみ
- 昭和22年:労働衛生基準法制定(当時は結核・赤痢・けい肺・重金属中毒防止)
- 昭和35年:じん肺法制定
- 昭和39年:中央労働災害防止協会設立
- 昭和47年:労働安全衛生法制定
平成4年に法改正され、健康管理体制整備として産業医の専門性の確保が図られている。
労働衛生対策の推進体制
- 産業医は、労働者数50人未満の事業場は選任義務がなく、医師に依頼して助言を受けることが困難。
地域産業保健センター事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業の3事業を一元化し、平成26年から産業保健総合センターを全国に設置している。
労働衛生管理の基本
- 労働衛生の3管理:作業環境管理、作業管理、健康管理
- 作業環境測定:昭和50年に作業環境測定士の資格が定められる
(測定計画・サンプリングなど作業環境評価基準が定められている)
事業場における労働衛生管理
- 事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医などを選任
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会設け毎月1回以上開催しなければならない。
- 平成11年:労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針が公表されている。

職業性疾病の予防対策
- 粉じん障害防止対策
昭和35年にじん肺法が制定され、昭和54年に粉じん障害防止規則が施行された。
平成30年度〜:第9次粉じん障害防止総合対策(5ヵ年計画)を実施。
じん肺健康診断は就業時、定期、定期外、離職時の4種がある。
都道府県労働局がじん肺管理区分を決定する。 - 電離放射線障害防止対策
慢性放射線皮膚障害や放射性造血器障害を引き起こすほか、白血病や皮膚がん、甲状腺がんなどを発症する可能性がある。
電離放射線障害防止規則:①外部被曝の防護、②内部被ばくの防護、③被曝管理、④特別な作業の管理、⑤健康管理、⑥安全衛生教育の実施などの措置を定めている。
福島原発事故への対応:現在は5年間につき100mSvを超えず、かつ1年間につき50m Svを超えてはならないことになっている。
国際放射線防護委員会(ICRP)では「定められた5年間の平均で20mSv/年、かついずれの1年においても50mSvを超えない」ことを勧告している。 - その他の職業性疾病
潜函病・潜水病、熱中症、騒音による難聴等、腰痛、振動障害、末梢循環障害・運動障害、VDT作業による視力障害・筋骨格系の症状・ストレス等による症状に対する労働衛生管理上重要である。
化学物質による健康障害防止対策
- 令和3年7月、厚生労働省の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書がまとめられる。
- 令和4年2月にリスクアセスメント対象物質を234追加。
4月1日現在:危険や健康障害を生じるおそれがあるのは674物質で、提供する者はSDSという安全データシートを交付しなければならない。 - ベンジジンや石綿については製造、輸入、使用等が禁止されている。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は製造に際し厚生労働大臣の許可が必要である。 - 有機溶剤中毒予防規則では、44種類を第1種、第2種、第3種に分類し作業主任者の選任、測定の実施、健康診断の実施、保護具の使用等を規定している。
- 特定化学物質障害予防規則では75種類が対象となっている(令和4年4月1日現在)
- 石綿については石綿肺や中皮腫、肺がんなどの健康障害を生ずる。
石綿の8割以上が建材による。
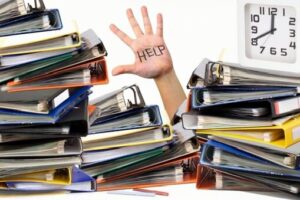
健康診断に基づく健康確保対策
一般健康診断:雇用時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者、給食従業員検便、自発的健康診断の6種類が労働安全衛生規則に定められている。
有所見率は年々増加し令和2年は58.5%(血中脂質が30%を超えている)
特殊健康診断としては:
- 有機溶剤業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛等業務
- 特定化学物質・製造禁止部物質
- 高圧室内業務と潜水業務
- 放射線業務
- 除染等業務
- 石綿等業務
離職者の健康管理としては申請により健康管理手帳が交付され、所有者に対して国が定期的な健康診断の受診機会を提供している。
令和2年のじん肺健康診断の有所見者数は1,116人(有所見率は0.4%:前年は0.6%)
労働災害補償と業務上疾病
- 労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して迅速かつ公正な保護をするための給付をしている。
(原則としてパート・アルバイト等を問わず労働者を使用するすべての事業に適用される) - 業務上疾病は労働基準法施行規則に認定基準が示されている。
- 労働災害は昭和36年をピークに長期的な減少傾向にある。
令和3年の死亡者数は867人で減少傾向だが、休業4日以上の死傷者数は近年増加傾向にある。 - 令和2年の内訳:「負傷に起因する疾病」が43.4%を占め、そのうち「災害性腰痛」が全体の37.1%を占める。
- 石綿については平成18年度をピークに肺がんが減少し、中皮腫は横ばい傾向にある。
- 精神障害等による労災認定件数は増加傾向にあり、脳・心臓疾患を上回っている。
その他の労働衛生対策等
- 過重労働による健康障害防止対策
平成26年に「過労死等防止対策推進法」が制定された。
平成30年に「働き方改革関連法」が成立し、月45時間、年360時間を原則とし、単月100時間未満を時間外労働の上限とする。 - 職場におけるメンタルヘルス対策
平成12年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」が策定される。
①心の健康づくり計画の策定およびセルフケア、②ラインによるケア、③事業場内産業保健スタッフによるケア、④事業場外資源によるケア の4つのケアが推進されてきた。
平成26年には労働安全衛生法が改正され、50人以上の労働者を使用する事業場に対し、ストレスチェックの実施が義務化された。 - トータル・ヘルス・プロモーション・プラン(THP)
昭和63年に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が策定された。
①健康保持増進計画の作成、②推進体制、③健康測定の実施、④健康指導の実施に取り組むことになった。 - 快適な職場環境の形成の促進
平成4年の労働安全衛生法改正で「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」が策定された。 - 職場における受動喫煙対策
平成30年に「健康増進法」が改正され、令和元年に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定された。 - 仕事と生活の調和
平成19年に「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。 - 治療と仕事の両立支援
平成28年に「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」が策定された(休暇制度・勤務制度の整備、就業上の配慮事項の決定等) - エイジフレンドリー
令和2年に「高年齢労働者安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」が公表され補助金も創設されている。 - 雇用保険制度
失業等給付や育児休業給付を支給する。
保険料は労働者と事業主双方が負担する。

文献
『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022、P348-368
医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022
一般財団法人 厚生労働統計協会「国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第69巻9号 通巻第1081号」、2022、P319-331
医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
車谷典男・松本泉美 編:「疫学・保健統計ー看護師・保健師・管理栄養士を目指すー」健帛社、2016

 hokenCから
hokenCから
コメント