 hokenC
hokenC今回は有病率・罹患率・死亡率・致命率・生存率などの疫学の指標について復習をしています。それぞれの特徴や計算方法などは、ここでしっかりと学習できると良いな〜と思います。
有病率:ある一時点において疾病を有している者の割合


有病率=観察時点における有病者数(人)➗ 観察時点における観察集団の人数(人)
=患者数 ➗ 人口



有病率は静態的な観察を通して、一時点の調査ができるため、罹患率と比べて容易に実施できるメリットがあります。
でも有病期間の短い疾患には適さないという特徴があります。
罹患率:一定期間内に新たな疾病が発生した率
罹患率=観察期間内に新発生した患者数(人)➗ 観察集団全員の観察期間の合計(人年)
=患者発生数 ➗ 人年



罹患率は動態的な観察を通して、疾病異常の発生を直接示しているため、因果関係を調べる際に用いることができます。
でも調査期間中の継続的な観察が必要となるため調査に困難を伴うという特徴があります。
累積罹患率:特定期間内に発症した者の割合を示す指標
累積罹患率=観察期間内に新発生した患者数(人)➗ 観察集団の観察開始時点の人数(人)
=患者発生数 ➗ 人口


死亡率:単位人口を一定期間(通常1年)観察したときの死亡発生の率
死亡率=観察集団内の死亡数(人)➗ 観察集団に対する観察期間の合計(人年)
=死亡者数 ➗ 人年
年齢調整死亡率:基準人口(昭和60年モデル人口)を基にして年齢構成を同等にして算出した死亡率
集団の死亡率を比較する場合、一方は高齢者の割合が多く、他方は若者の割合が多いと、両者の死亡率を正しく比較できているとはいえなくなります。このような場合は両者の集団の年齢構成をそろえて死亡率を計算する統計的な調整が行われます。これを「標準化」といいます。
致命率:対象とする疾病に罹患した者のうちその疾病が原因で死亡した者の割合
致命率=観察期間内のある疾病の死亡者数(人)➗ 観察期間内のある疾病の罹患者数(人)
=死亡者数 ➗ 罹患者数
生存率:対象とする疾病に罹患した者が、一定観察期間内に死亡から免れる確率
生存率=(1ー致命率)





疫学をもっと学習したい方は、こちらのアーカイブ記事も読んでみてください。
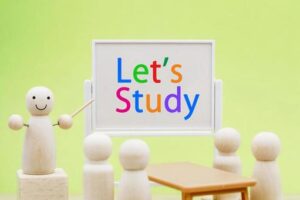
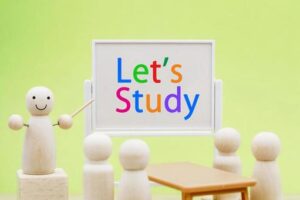
医療情報科学研究所(2022)「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア.
医療情報科学研究所 編(2022)「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」メディックメディア.
一般財団法人 構成労働統計協会(2022)「国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第69巻9号 通巻第1081号」.
医療情報研究所 編(2022)「公衆衛生がみえる 2022-2023」メディックメディア P12-14 .
標準保健師講座 編集室(2022)「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」医学書院.
荒井 直子 他 編(2022)「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」インターメディカル.
車谷典男・松本泉美 編(2016)「疫学・保健統計ー看護師・保健師・管理栄養士を目指すー」健帛社.

コメント